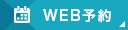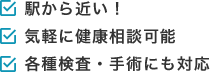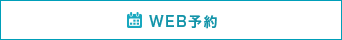近視になりやすい要素(仮説も含め)には、以下のようなものがあります。
1. 目の前後の長さが伸びる(眼軸長の伸長)
2. 近くを見る作業が増えてしまい、つらい状態が続く(調節負荷と近業作業)
・スマホや読書など近い距離での長時間作業を続ける→毛様体筋(ピント調整をする筋肉)が緊張し、調節負荷がかかる→脈絡膜の菲薄化、眼軸長の伸長が促される
3. 網膜に異常な指令が行く、ドーパミンの関与(Defocus & Dopamine Hypothesis)
・網膜が光のピントずれ(デフォーカス)を感知→眼軸長の成長を調節するシグナルが送られる
・近業作業過多→網膜の周辺部に遠視性デフォーカスが生じ、眼球が前後に伸びやすくなる
・屋外活動の減少によりドーパミン分泌が低下→眼軸の成長を抑制する働きが弱まり、近視が進行しやすくなる推察
4. 遺伝と環境の相互作用が起きる
・眼球の成長を制御する遺伝子の影響
・環境要因(長時間の近業作業、屋外活動不足など)によって、近視進行の加速
近視進行抑制の方法(研究中も含め)には、これらのものがあります。
1. 屋外活動の増加
・1日2時間以上の屋外活動は近視発症や進行を抑制する効果があるとの結果
2. 低濃度アトロピン点眼(0.01%、0.025%)
・50~60%の近視進行抑制効果の報告
3. オルソケラトロジー(角膜矯正療法、日中の裸眼視力を向上させる)
・夜間に特殊なハードコンタクトレンズを装用し角膜の形状を一時的に変える
・30~60%の近視進行抑制効果の報告
4. 多焦点ソフトコンタクトレンズ(特殊なデザインのソフトコンタクトレンズ)
・約30%の近視進行抑制効果の報告
5. DIMSレンズ(Defocus Incorporated Multiple Segmentsレンズ)
・52%の近視進行抑制効果の報告
6. EDOFデザインのソフトコンタクトレンズ
・Extended Depth of Focus(焦点深度を増加させる)デザインのソフトコンタクトレンズ
・24~32%の近視進行抑制効果の報告
7. レッドライト治療
・650nmの赤色光を用いて近視の進行を抑制する新しいアプローチ
・1年間の治療により、近視の進行が76.6%抑制された報告
8. バイオレットライト効果
・波長360~400nmの紫色の光
・網膜内の非視覚光受容体であるオプシン-5(OPN5)を刺激し、近視抑制因子であるearly growth response 1(EGR1)の発現を高め、近視の進行抑制に効果を持つ
◇理想と現実から未来に想うこと
日本において、人口増加が著しく核家族化も進み、住居が増えています。広々とした家は減少し、家と家は密集しがちで間隔も狭くなり、集合住宅が増え、遠くまで見渡せる環境は減りました。このため遠くを見続けることが少ない環境が増加している気がします。
暗いところで本を読むと目が悪くなるというイメージの大人も多数いらっしゃると思います。LEDの発達で周囲が暗い環境も少なくなっていますが、現在は暗所作業については特別マイナスなことを言われていません。現代は夜遅くまで明るく過ごせる場所が増えていますので、室内で近くを見る時間が増えているとは思います。あえて言えば、過度に明るい光は網膜にダメージを与えうるもので、暗めの環境自体は見づらさから起こる疲労などを除けば決して悪いとも言えません。
現代の人が近方作業を長時間しているのは、スマホ・タブレットや、パソコンのせいでしょうか?確かに昔は存在しなかったですが、本(さまざまな書物)は近方作業をさせるものとしてありました。異なる点として、スマホは簡単に多くの情報が手に入るため、エンターテイメント性も高く、長時間になりやすいと思います。ですが、昔も長時間にわたり本を読んでいた人はいたと思います。娯楽が少なかった分、書物による近方視をおこなっていた人は今よりも多かった可能性もあります。違いとしては、スマホはスワイプで文字がぶれたように見えながらスクロールしますが、本ではそれがありません。
電子機器は光の波長分布が自然光とは異なりますが、それが悪いかどうかはまだ解明されていません。自然界で物体は自分で発光するものと、それ以外に光を反射して見えているものがあります。自然発光する光は、大昔は太陽と火(室内ならろうそくの光)、数十年前まではそれと電球くらいでした。現在はパソコンなどの電子機器モニター光がそれに当たります。太陽も火も電球も普段直接は見続けない、まぶしいと目をそむけるものですが、モニター光だけは直接見続けます。これは現代に特徴的な目の環境になります。関係しているかは未だ不明ですが、これまで人間の目が経験したことのない状況を私たちは過ごしていることは確かです。
周辺視野のデフォーカス(ブレ)は検証が難しい部分です。眼鏡は中心と比べて周辺にぼやけが生じますし、メガネフレームの外側は裸眼の状態なので当然強めにぼやけています。その理屈からすると、コンタクトレンズ(CL)の方が眼鏡よりも近視進行抑制には優位性がありそうです。
オルソケラトロジーは夜間に装用し角膜を圧迫し形状を変形させるため、レンズが常に同じ位置にある必要があり、動きは最小限でなければなりません。本来のCLは動きがあることが推奨され、夜間は外すことが基本となりますので、どちらも異なっているオルソCLは眼科医としては疑問を感じてしまいます。ただし、かなり長い期間検証され、トラブルがごくまれであることは報告されています。私自身としてはトラブルがほとんど心配なくても、可能性があるものは使うべきかどうか、完全には結論を出せない状態です。
根本的な問題として特に小児にCLを装着させることは容易ではなく、CL治療はとても困難になることもあります。
他の特殊CLは、効果が実証されていけばすばらしいと思いますが、近視進行メカニズムが完全に解明されていない現在において、効果を言及することは難しいところです。
これらの内容から当院では現在、低濃度アトロピン0.01%(マイオピン)を扱っています。中期の経過ですが近視進行が少ない方が一定数おられ、効果と考えております。1年ごとに確認している眼軸長は伸長がマイルドな方が多めな印象です。
レッドライト治療は方法もシンプルで、この流れで解決すればすばらしいと感じています。これからの報告を期待したいです。機材が高価になるのと保険診療ではないので、もう少し待機か、積極的に治療できるところを見つけていくことになります。
バイオレットライトは、どれだけ日常と同じ程度にその光を取り入れられるかですが、UVカット、ブルーライトカットの状況が影響すると言われています。
仮定の話にはなりますが、気になるのが眼鏡、CLとの関連です。現代の眼鏡はほぼすべてがUVカットレンズになっています。バイオレット光も軽減させている可能性があります。眼鏡はフレームの周辺から光を取り入れられますが、基本的に目は正面を向いているため、バイオレット光の取り込みも減少すると推測されます。さらに、CLは角膜全体をカバーしていますので、瞳孔に入る全方向からの光の一部をカットするなど変化させる可能性があり、より影響があるとも推察されます。
住環境における窓ガラスもUVカット(紫外線からの保護は皮膚や水晶体を安全にする意味でそれ自体は効果があると考えます)が基本となっています。窓を閉めた室内空間自体が影響してしまう可能性もあります。その点から、窓の開放が近視進行抑制につながるために励行される未来も想像されます。さわやかな風を入れることが目の健康につながることが判明すればそれは驚きです。
外遊びの確保については、お子さんにとって、現代の日本では外遊びを長時間できる環境にはあまり多くなく、恵まれていないかもしれません。電子機器が発達し近方作業が多く、娯楽が多いと特に長時間の近方視になりうると思われます。屋外スポーツならば最も内容に合っていて外遊びに代わる最も理にかなう手段かもしれません。
こうして考えていくと、現代生活において避けづらい部分が多く存在し、どれも簡単に解決できない話であり、もどかしさを感じます。近視が減ることで、医療費の軽減、眼鏡・CLなど材料費の軽減、対応する時間の軽減、病的近視の軽減につながりますし、見やすい生活、眼鏡による周辺のゆがみやCL装着の違和感からの開放につながるはずです。原因として明確に判明すれば国として対応するような事象となるでしょう。原因究明と明確な予防方針の確立を期待したいと思います。
私ももちろん医療に携わる者として知識を増やしていきたいところです。様々な要素が絡むために究明が難しいですが、近視については私も小さい頃に避けたかった思いがあり、裸眼での良好な視力のあこがれもありました。若い人に負担の少ない時代が来るよう、何らかの要素を見つけていければと思っています。
他にも、強度近視だけの人と近視性網膜疾患が起こる人との違いは何か、片目だけ近視の人や明らかな度数の差がある人がいるのはなぜか、未解明ながら中高年で近視が減少する人がいますが、そのメカニズムは若い人に対しての近視改善アプローチにはなりうるかなど、近視についてはまだまだ興味あふれる不思議な世界が広がっています。少しでも解明に近づけたらと、日々患者さんからの情報に目と耳を研ぎ澄ませ、答えを探しながら診療しています。